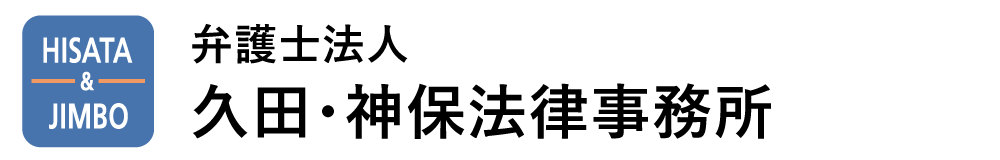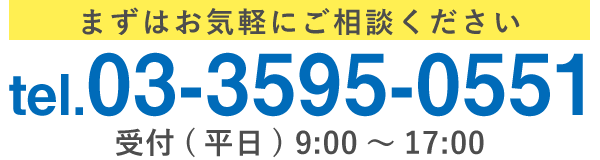中国法務コラム
2023-11-17
【中国法務コラム】データ越境流通の規範化及び促進に関する規定(意見募集稿)
2023-03-28
【中国法務コラム】中国現地法人における従業員の個人情報の管理
2023-03-10
【中国法務コラム】売買契約における所有権留保条項
2019-07-17
【中国法務コラム】「外商投資法」の概要
2018-11-15
【中国法務コラム】中国において労務派遣を利用する場合の注意点
2018-10-17
【中国法務コラム】中国企業との取引契約における紛争解決条項
2018-10-15
【中国法務コラム】中外合弁企業出資持分の第三者への譲渡
2018-08-03
【中国法務コラム】中国における会社董事の責任
2017-06-28
【中国法務コラム】中国における契約の解除事由
2015-08-28
【中国法務コラム】中国の時効制度
2015-08-05